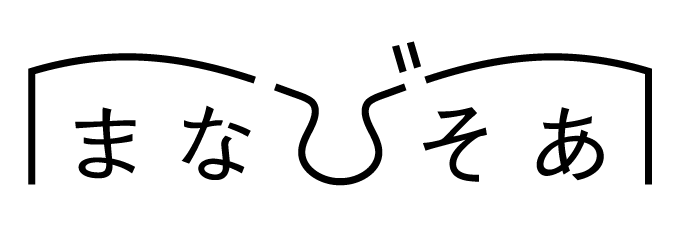2025/07/13 07:12
NIJIMIE筆は京田辺シュタイナー学校の美術教員の細井信宏先生による監修で、2年をかけて開発をしてきました。ここではその細井先生へのインタビューをご紹介します。長いインタビューですが、読み応えありますので是非お読みください!

Q. まず初めに細井先生がシュタイナー学校で美術教員になる経緯を教えてもらえますか?
子どもの頃から絵を描くのが好きで、大学では油絵を専攻しましたが、自分の表現を追求し作品を創ることに意味を見出せない日々が続いていました。
自己表現としての美術活動ではなく、もっと直接的に人や社会に貢献できるような美術活動がしたいけれども、どうすればよいのだろうか…。二十代は様々な本を読んだり海外へ行ったりボランティア活動などに取り組みながら、その答えを探し求めていました。
たまたま本屋で見つけたシュタイナ-の芸術教育に関する本をきっかけに、絵画造形療法が学べるイギリスの学校へ留学し、そこで美術が人や社会にいかに貢献できるかということを見出すことができました。
現在はその学びを基に『NPO法人京田辺シュタイナ-学校』や『curiousこども絵画造形クラス』などで美術講師として小学生から高校生を中心に美術を教えています。


Q. NIJIMIE筆の開発には2年かかりました。開発にあたって重視されたものは何ですか?また最終的に完成した製品はいかがですか?
まず毛の長さですが、溶き絵具をしっかり含んでくれて筆圧の調整も繊細にできることを考えた長さとなっています。毛質については馬毛などもっと質の良い毛を使えば更に良い筆は作れるかと思いますが(その点では妥協していると言えますが)、より多くの人に使っていただくために手ごろな価格でというところは大事な所だったのではないかと思います。

Q. 筆の柄は国産のヤマザクラを使い、また舐めても安心なオイル塗装を施しています。こうした様々な素材へのこだわりについてどのような印象をお持ちになられましたか?
ヤマザクラは日本で古くから愛されてきた野生の桜で、ソメイヨシノの親の木の一つとされています。山桜を愛でていると、その立ち姿から優しさや温もりを感じますが、ソメイヨシノにはあまり感じ取れないような「豊かな生命力」をも山桜からは感じ取ることができます。安心安全、野生、優しさ、温もり、生命力。子ども達にはぴったりの印象だと思います。また、この筆から子ども達に自然についてのいろんな話をするきっかけになるのではないかと思います。
Q. 太さ(11mm)、長さ、棒の形状など、筆を手で持って使うに当たって「柄の仕様」にも細井先生のこだわりを感じました。開発に当たってどのような点を重視されましたか?
例えば柄が細すぎると鉛筆を握っている時の様に指先で描いてしまう傾向が強くなり、部分的細かな表現やテクニックに傾倒してしまうことがあるので、ある程度の太さがあることで手先だけではなく腕を使って描けるような工夫をしました。また、柄にある程度の長さをもたせることで、毛先から離れたところを握ることにより、絵から一定の距離を保って描けるような工夫もしています。その際、洋筆の柄によくある見た目のデザイン性を重視した形状ではなく、どこを握っても同じ太さになるようなシンプルな形をしています。和筆にはよく竹の柄が使われますが、滲み絵技法は筆に水分を多くしみ込ませて描くので、竹の空洞から水が滴り落ちて絵に影響を及ぼしてしまう事があり、永く使用していると竹に亀裂が入ってしまうことから、木の柄としています。
Q. 最後に何かNIJIMIE筆についてコメントをいただけますか?
滲み絵筆としての質の面、コスト面でもとてもよいと思います。また、この筆には私達教員からの助言だけでなく、筆職人さんの素晴らしい技術、まなびそあお父さんメンバ-の多様な技巧と熱意が含まれた特別な筆ですので、使い続けたいと考えています。多くの方にも是非使っていただきたいと思います。

Q. 細井先生にNIJIMIE筆の開発の監修をお願いしたのは2022年10月でした。筆の開発をすることについて、当初どのようにお感じになりましたか?
画材を扱うお店には様々な筆が売られていますが、滲み絵技法に特化した筆はなく、適当な筆もなかなか見つけられなかったので、滲み絵専用の筆の制作はずっと待ち望んでいた素晴らしい機会だと思いました。
Q. にじみ絵とは何か?について少し解説いただけますか?
一般的に行われている乾いた画用紙の上に描く技法では、筆跡が線や形としてくっきり表れるので、子ども達は頭を使って意識的に何かを描こうとする傾向が優位になりますが、画用紙が濡れていると自然に滲み広がっていくことから、色が「どの様な感じ」なのかということに感覚を向けて描くことができるようになります。
Q. にじみ絵とは何か?について少し解説いただけますか?
一般的に行われている乾いた画用紙の上に描く技法では、筆跡が線や形としてくっきり表れるので、子ども達は頭を使って意識的に何かを描こうとする傾向が優位になりますが、画用紙が濡れていると自然に滲み広がっていくことから、色が「どの様な感じ」なのかということに感覚を向けて描くことができるようになります。
赤い絵の具で最初からリンゴやイチゴを描こうとすれば、物体の外観や表層の色に意識が留まってしまいますが、滲むことで色の美しさに気づき、その内的性質に感覚を向けていくことができるようになります。
このように滲み絵は物事の内的本質的な要素を感受する力を高めてくれます。今日では個人から発動する個性的表現や創造性、自由な表現などが重んじられる傾向にありますが、子どもの成長の初期においては表現すること以上に感受することが大事になってきます。息を吐くためにはその前にしっかりと吸わなければならないように、豊かな表現力を育てるためにはまず世界からの印象を受け止める感受性を培っていくことが大切であると考えます。
滲み絵はそういった子ども達の感受性を高めてくれる大切な芸術活動の一つとなっています。

Q. NIJIMIE筆の開発には2年かかりました。開発にあたって重視されたものは何ですか?また最終的に完成した製品はいかがですか?
まず毛の長さですが、溶き絵具をしっかり含んでくれて筆圧の調整も繊細にできることを考えた長さとなっています。毛質については馬毛などもっと質の良い毛を使えば更に良い筆は作れるかと思いますが(その点では妥協していると言えますが)、より多くの人に使っていただくために手ごろな価格でというところは大事な所だったのではないかと思います。
そのためには豚毛と山羊の毛を使ってというのが前提となっていました。丈夫で硬い豚毛は布地のキャンバスに粘性のある油彩で描くには適していますが、弾力がありすぎるので水彩には適しているとは言えず、山羊の毛は水彩筆として使用されていますが、柔らかすぎて滲み絵技法には使いづらい。
滲み絵技法としては、この弾性と柔らかさの両方の性質が必要なのですが、この対照的な2種の毛が果たして一つの筆の中に上手く調和できるのかは正直の所、難しいのではないかと思っていました。
何度も試作を重ねてもらいながら、適度な弾性を持ちながらも柔らかくしなやかな描き心地に改善できたのは、筆職人さんの匠の技あってのことだと感銘しました。

Q. 筆の柄は国産のヤマザクラを使い、また舐めても安心なオイル塗装を施しています。こうした様々な素材へのこだわりについてどのような印象をお持ちになられましたか?
ヤマザクラは日本で古くから愛されてきた野生の桜で、ソメイヨシノの親の木の一つとされています。山桜を愛でていると、その立ち姿から優しさや温もりを感じますが、ソメイヨシノにはあまり感じ取れないような「豊かな生命力」をも山桜からは感じ取ることができます。安心安全、野生、優しさ、温もり、生命力。子ども達にはぴったりの印象だと思います。また、この筆から子ども達に自然についてのいろんな話をするきっかけになるのではないかと思います。
Q. 太さ(11mm)、長さ、棒の形状など、筆を手で持って使うに当たって「柄の仕様」にも細井先生のこだわりを感じました。開発に当たってどのような点を重視されましたか?
例えば柄が細すぎると鉛筆を握っている時の様に指先で描いてしまう傾向が強くなり、部分的細かな表現やテクニックに傾倒してしまうことがあるので、ある程度の太さがあることで手先だけではなく腕を使って描けるような工夫をしました。また、柄にある程度の長さをもたせることで、毛先から離れたところを握ることにより、絵から一定の距離を保って描けるような工夫もしています。その際、洋筆の柄によくある見た目のデザイン性を重視した形状ではなく、どこを握っても同じ太さになるようなシンプルな形をしています。和筆にはよく竹の柄が使われますが、滲み絵技法は筆に水分を多くしみ込ませて描くので、竹の空洞から水が滴り落ちて絵に影響を及ぼしてしまう事があり、永く使用していると竹に亀裂が入ってしまうことから、木の柄としています。

Q. 最後に何かNIJIMIE筆についてコメントをいただけますか?
滲み絵筆としての質の面、コスト面でもとてもよいと思います。また、この筆には私達教員からの助言だけでなく、筆職人さんの素晴らしい技術、まなびそあお父さんメンバ-の多様な技巧と熱意が含まれた特別な筆ですので、使い続けたいと考えています。多くの方にも是非使っていただきたいと思います。